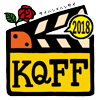クィアな仲間とは、目の前にある、「普通」とは異なる社会的つながりを共に想像できる仲間
邦題:クィアな仲間の作り方
英題: Thick Relations
監督:ジュールズ ロスカム Jules Rosskam
85分|2012年|米国|英語
私が京都で大学生をしていた頃、毎日でも会えるクィアな仲間がたくさんいた。時間を気にせず朝まで呑み、誰かの家で眠り、起きて、それぞれ大学やバイトへ飛び出して行く。そしてまた誰からともなく集まり、同じことを繰り返す。言いたいことも言い合って、時には喧嘩もする、気の置けない仲間たちだった。ジュールス・ロスカムの3作品目である『クィアな仲間の作り方(Thick Relations)』は、そんな懐かしい日々のことを思い出させてくれる。
ヴィヴィ、ルビー、ジャックス。この映画は、シカゴに住む等身大のクィアたち3人の生活の様子を、ドキュメンタリーのようなタッチで切り取る。トランスジェンダー・プライドの旗のような、淡いピンク・ブルー・白が折り重なる美しい水平線から始まるこの映画は、賑やかな夕食会のシーンや朝の起き抜けのベッドのシーン、あるいは行きつけのクィア・バーで歓談するシーンなど、3人の「ホーム」を順番に映し出す。登場人物たちは淡々と朝食の用意をし、部屋の掃除をし、そして夜の街へと繰り出して行く。特に事件が起きるわけでも、誰かが大恋愛 (または大失恋!)をするわけでもない。それでも、この作品にはホーム・ムービーのような不思議な魅力がある。初めて出会う登場人物の日常に、観客である私たちは気が付けばそっと引き込まれ、おしゃべりをしている気分になる。そんな魔法のようなクィア映画なのだ。
クィアな仲間の作り方
ついこの間まで毎週末のようにクラブやバーへ繰り出していた友達が、パートナーが出来た途端に疎遠になり、ブラックホールに飲み込まれたかのように(ほぼ)音信不通になる、そんな経験が私にはしょっちゅうある。友達に「フラれ」続けた結果、私にとってのクィアな仲間というのは、単に非シスであったり非ヘテロであることだけを共有する友達ではない、と言うことを(今更ではあるが)考えるようになった。誰とどのような関係を築いて行くのかを積極的に思考し続け、自分が大切だと思う人それぞれと誠意ある関係を続けていくこと。クィアな仲間とは、目の前にある、「普通」とは異なる社会的つながりを共に想像できる仲間なのではないだろうか。
この映画に登場するクィアたちが問いかけるのは、まさにその「つながり」の在り方だ。監督自身、この映画はChosen Familyを扱った映画であると言う。Chosen Familyとは英語圏のクィア界隈でよく使われる、血縁や法的なつながりとは別の、今、自分が「選んだ」家族と言う意味の言葉だ。監督の指摘通り、主人公3人とその周りの人々の関係は、友達や恋人といったカテゴリーでは包摂しきれない太い結びつきや連帯を拠り所としている。互いに許しあい・助け合いながら、この映画は、時間・場所・経験を共有する3人の特別なかかわりあいを映し出す。クィアな仲間たるものの可能性、そしてその在り方の一例を見せてくれるのだ。
ケア・マネージャーとして働くジャックスは、冒頭の夕食会の場面にて新しいステディなパートナーとの関係性を周囲に打ち明ける。が、別の場面でジャックスは掲示板で探したセックスの相手とのデートを前に胸を踊らす。もはや言うまでもなく、クィアな親密性は多様な形の欲望と共存する。そこに肉体関係があるかどうかは関係ない。どの程度オープンな関係性をパートナー(単数でも複数でも)と築いていくのかは、自分が相手との誠実な対話を通して決めていくだけのことである。喜びと愛に溢れたジャックスは、いざデートへ繰り出さんとする時にだって「ルビーによろしく伝えて」と親友ヴィヴィに言い残すことを忘れない。自分にとって大事な人は誰か、その人たちと信頼できる関係をどう築いて行くのか。単純な問いだけれども、忘れがちなこと。それを、この映画は思い出させてくれる。
もちろん、親密な関係性が永遠に続く保証はない。今「自分が選んだ家族」のChosen Familyだって、時間の流れと共に、ゆくゆくはその形や、その構成員にとっての意味を変えることもあるだろう。作中には時折、エモーショナルなテキストのメッセージが挟まれる。作品内の他の映像と直接の関係があるのかは分からない。ただ一つ分かるのは、それが、今、自分の側にはもういない大切な人に向けたメッセージだと言うことだ。誰の喜びの裏にも、辛い別れの悲しみがあるだろう。それは昔の恋人かも、家族かも、友達かもしれない。その別れがどんなにネガティブなものだったとしても、その人が自分にとって大事な人だったという事実は変わらない。このテキストを見て、あなたは誰のことを考えるのだろうか。
クィアな映画の作り方
上に書いた通り、この映画に明瞭な起承転結はない(がしかし、クィア・コーラスのコンサートという素敵なフィナーレはある)。物語が問題解決に向かって進んでいく、わかりやすいフィクションやドキュメンタリーを見慣れている人にとっては、この作品の流れが、ちょっと良く分かんねーなと感じられるかもしれない。けれども私は、そんな「分かりにくさ」が実はクィア的な要素としてこの映画内に意図的に散りばめられているのではないかと考えた。そこで、『クィアな仲間の作り方』が映像的にもどうクィアであるのか、という点について私なりの解釈をここに加えたい。もちろん少し専門的な話になってしまうので、興味がなければ読み飛ばしてもらっても構わない。
フランスの映像作家であり映像理論家でもあるジャン・アプスタインは、「映像の世界は意のままに拡大・縮小し、早送りされたりスローモーションで映し出されたりすることで、柔軟性・粘性・そして流動性のある卓越した領域を構成する」と論じた。つまり、映画的再生産の過程においては、明確な定義のない、形の流動的な曖昧なモノを曖昧なまま、作り手から受け手へと伝達することが可能となる。そもそも「クィア」とは、「こうである」と言う画一的な不動のラベルを貼ることに対して懐疑的な、「こうでもなければこうでもない」流動的な属性の集合体を指す。『クィアな仲間の作り方』の映画が取り扱うのは、そんな無形で曖昧な「クィア」の概念であり、クィアたちの紡ぐ関係性であり、それが「型にハマらない」映像となって現れる。
本作において、役ごとの設定やセリフがどこまで存在したのかはわからない。が、出演者はいたって自然体にそれぞれの生活を送る。その姿はまるで、登場人物が自分自身を演じているようにも見える。ドキュメンタリーのような、そうでないような場面が続き、この映画は現実とフィクションの境界線を往来する。時系列に進む出来事もあるが、それぞれの場面にどのような時間的繋がりがあるかは、明らかでは無い。観客は、その「ストーリー」上の構成のあやふやさを受け入れなくてはならない。さらに言えば映像間の物理的な区切りも、時間が経つにつれて徐々に曖昧になる。
本映画内には突然のセックス・シーンも挟まれるが、激しい喘ぎ声からソレと分かるものの、被写体とカメラの距離が近いため、具体的に誰が誰と何をしているのか特定はできない。セックスシーンの喘ぎ声と、そして本作の軸とも言えるクィアコーラスの練習のシーンは、時折その音のみが画面上に残り、3人それぞれの生活に染み渡る。喘ぎ声は、それが重ねられるシーンに登場する人物のものかもしれないし、別の人のものかもしれない。幾層にも重なる和声の歌声も、その歌詞が誰のどの心境を代弁しているか、明示的に提示されることは無い。シーンとシーンの間の画面上の境界線が不分明になることで、各場面の時間的・空間的な独立性が薄れ、混ざり合う。映像レベルで故意的に引き起こされる画面の衝突やすれ違い、重なり合いは、本来こうした映画に置かれるであろう語りの期待を優しく攪拌する。
作品の構造だけでなく、映像内の表象にも流動的な「クィア」要素がある。例えば、ヴィヴィとその旧友・エミットがビーチに泳ぎに行くシーンがそれだ。水は時に固まり、蒸発し、そして合体する。液体のままで一つの形を保つことは無く、でたらめな方向に向かって自由に動く性質を持つ。そんな不定のもっともたる見事なシンボリズムの水(湖)を前に、ヴィヴィとその旧友・エミットは自らのトランス・アイデンティティについて話し合う。作品内に、登場人物の誰が「何者であるか」に触れるシーンは一切無い。セクシュアリティやジェンダー・アイデンティティは、自分で決めても、決めなくてもいい。それが水のように移ろい行くものであることを示唆するかのように、画面の奥に広がる湖は、それぞれの水着ではしゃぐ2人を柔らかく包み込む。
終わりに
大学を卒業して何年も経ち、結果的に全員が京都を離れ、学生時代のクィア仲間とは数年に一度会うきりになってしまった。それでも、お互いに自由で、開放的で、それでいて信頼し合っていたあの家族のようなあの時の関係性のことを今でもよく考える。ゆくゆくは結婚・そして家族という社会単位へと回収されがちなヘテロの恋愛関係とは違い、生産的な「目的」を持たず、貸し借りのない、可能性に満ち溢れたつながり。それはまるで生き物のように息をし、膨張と収縮を繰り返す、オーガニックな関係性だった。『クィアな仲間の作り方』の見所はそんな開かれた人間関係であると同時に、その「クィア」的な関係性を映像レベルに落とし込んだ作品構成である。この作品では物語が一つのクライマックスに向かって進む代わりに、シーンの一つ一つが満天の空の星のようにそれぞれ別の輝きを放ち、そして星座のように結ばれる。2019年のクィア映画祭では、ぜひ『クィアな仲間の作り方』を見て、クィアな親密性とクィアな映画づくりとの交差点に想いを馳せてほしい。
 岸茉利
岸茉利
大学時代より関西クィア映画祭で字幕翻訳を始める。卒業後は東京で就職するも、2年半で退職し渡仏。フランス語を学んだのち、映画好きが高じてパリで映画学の修士号を取得。国家権力や社会政治が視覚文化、特にジェンダーの表象とどう関係し合うのかを研究している。2019年よりボストンで東アジア映画・メディア研究の博士課程に進学予定。
『クィアな仲間の作り方』
 クィアな仲間とは、目の前にある、「普通」とは異なる社会的つながりを共に想像できる仲間
クィアな仲間とは、目の前にある、「普通」とは異なる社会的つながりを共に想像できる仲間岸茉利
 時々「やっぱり私たちってクィアだね」とふと肩の力を抜いて笑う瞬間がある
時々「やっぱり私たちってクィアだね」とふと肩の力を抜いて笑う瞬間があるあやこ